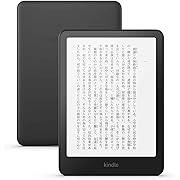信長の居城変遷:那古野城から安土城まで
織田信長の生涯を辿る上で、彼が居城とした城郭の変遷は、その権力の拡大と野望の軌跡を物語る重要な指標となります。幼少期の那古野城から最終的な安土城まで、それぞれの城は信長の成長と共に、より壮大で象徴的な存在へと発展していきました。
幼少期から尾張統一まで:那古野城・清洲城での基盤固め
信長が最初に居住したのは、現在の名古屋市中区にあった那古野城でした。この城は信長の父・織田信秀が今川氏豊から奪取した城で、信長は幼少期から青年期にかけてここで過ごしました。那古野城は尾張国の中心部に位置し、商業都市として栄えていた地域にあったため、信長の商業的感覚や革新的な思考の基盤が形成された場所とも言えるでしょう。
1555年、信長は清洲城へと居城を移しました。清洲城への移転は、単なる居住地の変更以上の意味を持っていました。この城は尾張国の守護代である織田大和守家の本拠地であり、信長がここを手に入れることで尾張国内での地位を大きく向上させることができたのです。清洲城は戦国時代を通じて「尾張の中心」とも呼ばれる重要な拠点でした。
清洲城時代の信長は、桶狭間の戦いという歴史的な勝利を収めました。1560年のこの戦いで今川義元を討ち取ったことにより、信長の名は一気に全国に知れ渡ることになります。また、清洲城を拠点として尾張国内の統一を進め、隣国への進出の足がかりを築いていきました。この時期の信長にとって清洲城は、単なる居住地ではなく、天下統一への第一歩を踏み出すための重要な戦略拠点だったのです。
天下統一への野望:岐阜城から安土城へと続く権力の象徴
1567年、信長は美濃国を攻略し、稲葉山城を岐阜城と改名して新たな居城としました。この岐阜という地名は、中国の故事にちなんで信長自身が命名したとされ、天下統一への強い意志を表現したものでした。岐阜城は標高329メートルの金華山頂上に築かれた山城で、眼下に広がる濃尾平野を一望できる絶好の立地にありました。ここから信長は「天下布武」の印章を用いるようになり、全国統一への野望を明確に示すようになったのです。
岐阜城時代の信長は、まさに破竹の勢いで勢力を拡大していきました。足利義昭を奉じて上洛を果たし、京都の政治に深く関与するようになります。また、比叡山焼き討ちや一向一揆との戦いなど、宗教勢力との激しい対立も この時期の特徴でした。岐阜城はこうした信長の積極的な軍事行動の司令部として機能し、彼の権威の象徴でもありました。
1576年、信長は最後の居城となる安土城の建設に着手しました。琵琶湖畔の安土山に築かれたこの城は、それまでの戦国時代の城とは一線を画す革新的な設計でした。7層の天主(天守)を持つ安土城は、まさに信長の権力と美意識の結晶であり、当時の人々に強烈な印象を与えました。金箔で装飾された豪華絢爛な内装や、西洋の文化を取り入れた斬新な意匠は、信長が目指した新しい時代の象徴でもありました。安土城は完成からわずか3年後の本能寺の変で焼失してしまいましたが、その短い期間に日本の城郭建築に革命をもたらし、後の時代の城づくりに大きな影響を与え続けています。