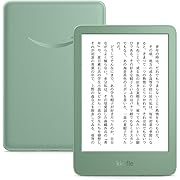森蘭丸ら小姓たちが見た信長の素顔
戦国時代の覇者・織田信長といえば、比叡山焼き討ちや一向一揆の弾圧など、「第六天魔王」と呼ばれた冷酷無比な武将としてのイメージが強い。しかし、彼の身近に仕えた森蘭丸をはじめとする小姓たちが目にしていたのは、歴史書に記される残酷な権力者とは異なる、もう一つの信長の顔だった。
戦場では冷酷無比、しかし小姓たちには意外にも優しい父親のような一面を見せていた信長
信長は戦場や政治の場では確かに苛烈な判断を下す武将だったが、日常生活では小姓たちに対して驚くほど温和な態度を見せていたという。森蘭丸の兄である森可成が信長のために戦死した後も、信長は蘭丸ら森家の子弟を手厚く保護し、まるで自分の息子のように可愛がった。特に蘭丸に対しては、その聡明さと忠誠心を高く評価し、重要な書状の管理や来客との応対まで任せるほどの信頼を寄せていた。
小姓たちの証言によれば、信長は彼らの教育にも熱心で、武芸はもちろんのこと、読み書きや礼儀作法まで丁寧に指導していたという。時には自ら筆を取って手本を示したり、間違いを犯した小姓に対しても決して声を荒げることなく、なぜそれが間違いなのかを論理的に説明する姿があった。これは、家臣に対しては容赦ない処罰を下すことで知られた信長の、全く別の一面である。
また、信長は小姓たちの体調管理にも気を配っていた。蘭丸が風邪を引いた際には、自ら薬を調合して与えたという逸話も残されている。戦国武将としては珍しいほどの細やかな配慮を示し、小姓たちからは「お父様のようだった」と慕われていたのである。こうした日常の姿は、権力闘争の激しい戦国時代にあって、信長が心を許せる相手を求めていた証拠でもあろう。
茶の湯や能楽を愛し、蘭丸らと文化談義に興じる教養深い武将としての知られざる姿
一般的には革新的で実利主義者として知られる信長だが、実は古典文化に対する造詣も深く、特に茶の湯と能楽には並々ならぬ情熱を注いでいた。蘭丸の日記には、信長が千利休らの茶人と茶会を開く際に、小姓たちにも茶の心得を教えている様子が詳細に記されている。信長は茶器の美しさや茶の味わいについて語る時、戦場での厳しい表情とは打って変わって、まるで少年のような輝く瞳を見せていたという。
能楽に対する信長の愛好ぶりも、小姓たちの証言から明らかになっている。安土城では定期的に能の公演が催され、信長自身も舞台に立つことがあった。蘭丸らは主君の稽古相手を務めることもあり、その際の信長は芸事に打ち込む純粋な表情を見せていた。「敦盛」を舞う信長の姿は、「人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」の一節とともに、小姓たちの心に深く刻まれている。
さらに興味深いのは、信長が小姓たちと古典文学について語り合う場面である。蘭丸は特に和歌の才能があったため、信長はしばしば歌会を開いて文学談議に花を咲かせていた。『源氏物語』や『平家物語』の一節を引用しながら、人生の無常や美しさについて語る信長の姿は、まさに教養人そのものだった。こうした文化的な側面は、信長の人格形成において重要な要素であり、彼の政治的判断にも少なからず影響を与えていたと考えられる。