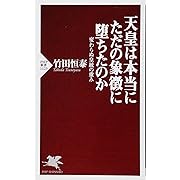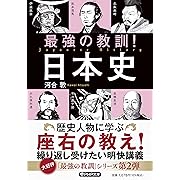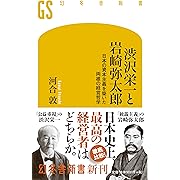岐阜城から見る信長の美濃攻略戦略
稲葉山城から岐阜城へ〜信長が見据えた天下統一への拠点
織田信長が美濃国攻略の最終目標とした稲葉山城は、斎藤道三が築いた要塞として美濃平野を見下ろす絶好の立地にありました。この城は金華山の頂上に位置し、眼下には長良川が蛇行して流れ、東西南北すべての街道を監視できる戦略的な要衝でした。道三の死後、息子の斎藤義龍、そして孫の斎藤龍興が居城としていましたが、信長はこの城こそが美濃制圧の鍵であることを早くから見抜いていました。
永禄10年(1567年)、ついに稲葉山城を攻略した信長は、すぐさま城の大改修に着手します。彼は単なる地方の山城としてではなく、天下統一への前進基地として生まれ変わらせることを構想していました。城下町の整備にも力を入れ、商工業者を積極的に呼び寄せて経済基盤の強化を図ります。この時期の信長の動きを見ると、美濃攻略が単なる領土拡張ではなく、より大きな野望への布石であったことがよくわかります。
城名を「岐阜」と改めたのも、信長の深い思慮の表れでした。中国の故事「周の文王が岐山より起こって天下を平定した」に由来するこの命名は、自らの天下統一への意志を内外に示すものでした。また「阜」の字には「丘」という意味があり、金華山の地形的特徴も表現しています。信長は岐阜城を拠点として、東は甲斐の武田氏、北は越前の朝倉氏、西は畿内への進出を睨んでいました。この立地選択こそが、後の天下布武への道筋を決定づけたのです。
美濃三人衆の調略と長良川を活かした戦略的な城郭配置
信長の美濃攻略において最も重要な転換点となったのが、美濃三人衆と呼ばれる稲葉一鉄、氏家卜全、安藤守就の調略でした。彼らは斎藤氏の重臣でありながら、若い斎藤龍興の統治に不満を抱いていました。信長はこの機を逃さず、政略結婚や経済的な優遇措置を通じて彼らを味方に引き入れます。特に稲葉一鉄は清洲城での会談で信長の器量に感服し、以後忠実な家臣として仕えることになりました。
長良川の水運を活用した兵站戦略も、信長の美濃攻略を語る上で欠かせない要素です。信長は木曽川と長良川の合流点付近に前線基地を設け、船による物資輸送ルートを確保しました。これにより大軍の長期展開が可能となり、従来の短期決戦型の攻城戦から、持久戦も視野に入れた柔軟な作戦展開ができるようになりました。河川交通の掌握は、単に軍事的な優位性だけでなく、商業活動の活性化にもつながりました。
城郭配置においても、信長は長良川流域に沿って支城群を戦略的に配置しています。墨俣城の築城で有名な一夜城の逸話も、実際には継続的な築城活動の一環として理解すべきでしょう。信長は河川沿いの要所要所に砦や陣屋を設け、相互に連携できるネットワークを構築しました。この城郭群は稲葉山城攻略時の包囲網としてだけでなく、攻略後の美濃支配においても重要な役割を果たします。岐阜城を頂点とするこの城郭ネットワークは、後に信長が展開する広域支配システムの原型となったのです。