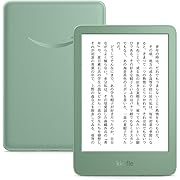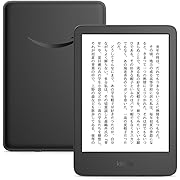信長の遺体はなぜ見つからなかったのか
織田信長の最期を語る上で、最も謎に満ちているのが遺体の行方です。天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変で信長は明智光秀の謀反により命を落としましたが、その遺体は今日に至るまで発見されていません。この歴史上最大級の謎について、様々な説が唱えられてきました。
当時の記録を見ると、信長の遺体捜索は事件直後から精力的に行われていたことがわかります。羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)は中国大返しで京都に戻ると、すぐに本能寺跡での捜索を命じました。しかし、どれだけ探しても信長の遺体らしきものは見つからず、関係者を困惑させたのです。
この遺体消失の謎は、単なる歴史的好奇心を超えて、戦国時代の政治情勢にも大きな影響を与えました。遺体が見つからないことで、信長の死を疑う声も上がり、各地の大名たちの動向にも微妙な変化をもたらしたのです。現代においても、この謎は多くの研究者や歴史愛好家の関心を集め続けています。
本能寺の変当日、炎上する寺院から遺体を運び出すことは困難で、完全に焼失した可能性が高い
本能寺の変当日の状況を詳しく見ると、遺体が発見されない理由の一つとして、激しい火災による完全焼失説が最も有力視されています。明智軍の攻撃を受けた本能寺は、瞬く間に炎に包まれました。当時の建物は木造で、一度火がつくと燃え広がるのは非常に早く、寺院全体が猛烈な勢いで燃え上がったのです。
信長は最期まで戦い抜いた後、炎に囲まれた奥の間で自害したと伝えられています。その時点で既に寺院の大部分が火に包まれており、遺体を安全な場所に運び出すことは物理的に不可能な状況でした。炎の温度は非常に高く、木材だけでなく人体も完全に灰になるほどの熱量があったと考えられています。
さらに、当時の火災の規模を物語る証言も残されています。近隣の住民たちは、本能寺の火災を「天を焦がすほどの大火」と表現し、その激しさを後世に伝えています。このような状況下では、骨や歯といった通常火災でも残りやすい部分さえも、完全に灰と化してしまった可能性が高いのです。現代の科学的知見からも、長時間にわたる高温での燃焼は、人体を跡形もなく消失させることが可能であることが証明されています。
明智光秀が証拠隠滅を図り、信長の首を持ち去ったという説も有力視されている
一方で、明智光秀が戦略的に信長の遺体を処理したという説も、多くの歴史研究者によって支持されています。光秀にとって信長の死は、自らの謀反の正当性を示す重要な証拠でした。しかし同時に、信長の遺体が敵方の手に渡ることで、政治的に不利な状況に陥ることも十分に予想できたのです。そのため、光秀は意図的に信長の首を持ち去り、秘密裏に処分した可能性が指摘されています。
戦国時代の慣習として、討ち取った敵将の首は戦功の証として非常に重要視されていました。特に信長ほどの大物であれば、その首は計り知れない政治的価値を持っていたはずです。光秀は経験豊富な武将であり、このような政治的駆け引きの重要性を十分理解していました。そのため、部下に命じて火災の混乱に紛れて信長の首を回収させ、後に密かに埋葬したという説が成り立つのです。
この説を裏付ける状況証拠として、光秀の行動パターンも挙げられます。本能寺の変の後、光秀は異常なほど迅速に京都の掌握に動いており、事前に綿密な計画を立てていたことがうかがえます。そのような周到な準備をしていた光秀が、信長の遺体処理についても計画していたと考えるのは自然なことです。また、当時の文献の中には、光秀の家臣が「重要な物」を運び出したという曖昧な記述もあり、これが信長の首を指している可能性も否定できません。