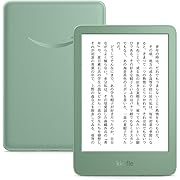信長と濃姫:政略結婚から始まった夫婦の絆
戦国時代の政略結婚から生まれた、織田信長と濃姫の意外にも深い夫婦愛の物語
戦国時代の結婚といえば、家同士の利益を重視した政略結婚が当たり前でした。織田信長と濃姫(帰蝶)の結婚も、まさにそうした時代背景の中で生まれたものです。天文17年(1548年)頃、信長が15歳前後、濃姫が14歳頃のことでした。この結婚は、美濃の戦国大名・斎藤道三と尾張の織田信秀(信長の父)との同盟を固めるための重要な政治的取り決めだったのです。
当時の信長は「うつけ者」と呼ばれ、奇抜な格好や行動で周囲を困らせる若者でした。一方の濃姫は、「美濃のマムシ」と恐れられた斎藤道三の娘として、きっと相当な覚悟を持って尾張に嫁いできたことでしょう。最初は互いに警戒心を抱いていたかもしれません。しかし、この政略結婚が後に戦国史上でも珍しいほどの夫婦の絆を育むことになるとは、誰も予想していなかったはずです。
興味深いことに、信長は生涯にわたって濃姫を正室として大切にし続けました。戦国武将の多くが政治的必要に応じて正室を変えることもあった時代において、これは非常に珍しいことでした。二人の間に子どもは生まれませんでしたが、それでも信長が濃姫への愛情を失うことはありませんでした。政略から始まった結婚が、いつしか真の愛情に変わっていったのかもしれません。
美濃の姫君と尾張の若武者が築いた絆―史料から読み解く二人の真実の関係
史料を詳しく調べてみると、信長と濃姫の関係性の深さを物語るエピソードがいくつも見つかります。特に注目すべきは、濃姫の父である斎藤道三が息子の義龍と対立し、最終的に討死した際の信長の行動です。信長は義父を助けるために出兵し、道三の死後も濃姫の心情を深く理解し、支え続けました。これは単なる政治的配慮を超えた、夫としての愛情の表れと見ることができるでしょう。
また、信長が各地を転戦する際にも、濃姫は常に信長の居城に留まり、内政を支えていました。安土城を築いた際には、濃姫のための特別な居住空間が設けられていたという記録も残っています。信長は多くの側室を持ちましたが、それでも濃姫の地位が揺らぐことは一度もありませんでした。これは戦国時代の夫婦関係としては極めて異例のことで、二人の間に特別な信頼関係があったことを示しています。
さらに興味深いのは、濃姫が信長の政治的判断にも影響を与えていたという説があることです。美濃出身である濃姫の助言が、信長の美濃攻略や近畿地方での戦略に活かされていた可能性があります。単なる飾り物の正室ではなく、信長の政治的パートナーとしての側面も持っていたのかもしれません。本能寺の変で信長が討死した後、濃姫がどのような人生を送ったかについては諸説ありますが、夫への深い愛情を最後まで貫いたという話が今も語り継がれています。